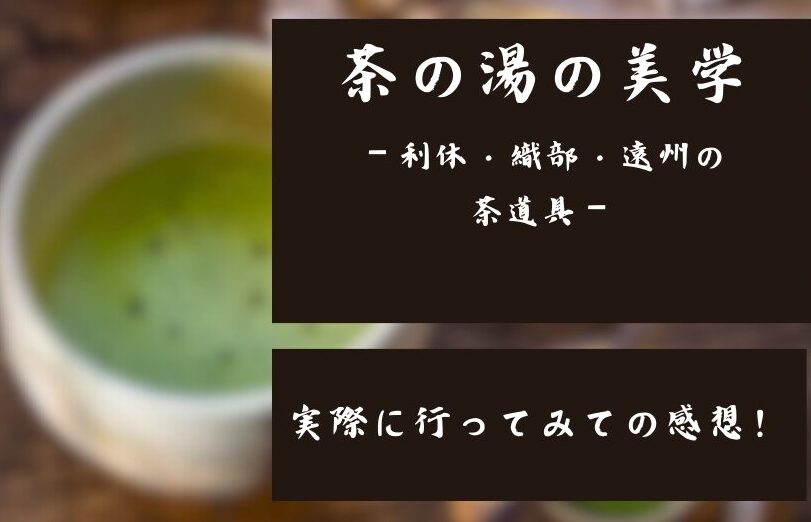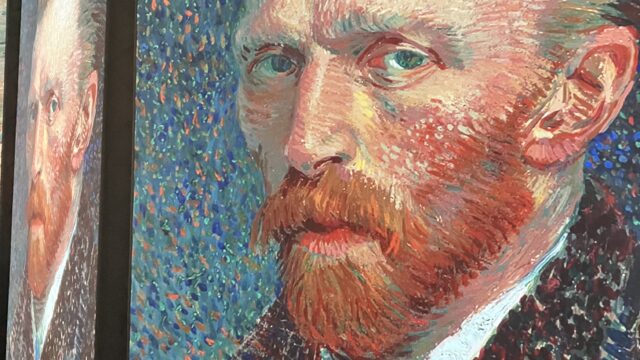こんにちは!
茶道男児です。
今回は現在開催中(2024年6月16日まで)の茶の湯の美学ー利休・織部・遠州の茶道具ー展に行ってみての感想レポートになります。
安土桃山時代から江戸時代初期に、茶の湯界を席巻した、千利休・古田織部・小堀遠州の美意識を三井家伝来の茶道具から深める展示会となっています。
普段滅多に見ることができない展示物など、見所が多数でしたのでこれから行く方の参考になると嬉しいです。
それではレッツゴー!
この記事はこんな人におすすめ
・茶の湯の美学展に興味があるが、迷っている方
・茶道の歴史を学びたい方
開催概要
- 会期:令和6年4月18日(木)〜6月16日(日)
- 開館時間:10:00〜17:00(入館は16:30まで)
- 休館日:月曜日
- 主催:三井記念美術館
- ホームページ:https://www.mitsui-museum.jp/press/release/release_240418.pdf
- 入館料:一般1,200円/大学・高校生700円/中学生以下無料
- ※70歳以上の方は1,000円(証明要)
- 会場:三井記念美術館
- 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1−1 三井本館 7階 https://maps.app.goo.gl/5hSnWDqKPKMTiXUk6
展示構成と所用時間について
今回の展示会では、各展示室でテーマが決められており7つのブースに分かれています。
⭐️展示室1:利休・織部・遠州の美意識
⭐️展示室2:国宝の名碗
展示室3:如庵 織田有楽の茶室
⭐️展示室4:千利休の美意識=わび・さびの美
⭐️展示室5:古田織部の美意識=破格の美
展示室6:数棗と数香合
展示室7:小堀遠州の美意識=綺麗さび
所用時間としては概ね1時間〜1時間半で十分に鑑賞できる内容となっています。
途中、軽く休憩ができる長椅子もあったので一休みすることも可能です。
私が特に面白かったのは、⭐️をつけた展示室1・2・4・5でした。
次の章で、さらに詳しく深掘りしていきます!
千利休・古田織部・小堀遠州の美意識とは
千利休
まず最初にご紹介したいのは、茶の湯の祖「千利休」にです。
堺の魚問屋の息子として生まれた利休は、茶の湯を北向道陳(きたむきどうちん)に学び、武野紹鴎(たけのじょうおう)を師とすることで茶の湯を大成させていきました。
なかでも利休の美意識は「わび・さびの美」として評されており、人や物のありのままをみることで質素で控えめな美しさを称賛する考え方であり、物事の中にある不完全さや無常性を通じて生まれる美しさを表現しています。
古田織部
古田織部は、信長・秀吉・家康に仕えた美濃出身の大名茶人です。
利休に茶を学んだ利休七哲の一人とされています。
織部の美意識は、利休の美意識を踏襲しながらも、その規格を破る「破格の美」と言われています。
織部好みと呼ばれるゆがみある茶陶には、ダイナミックな強さが垣間見える独特な世界観を楽しむことができます。
小堀遠州
小堀遠州は、近江国出身で名古屋城・江戸城・二条城など、多くの作事奉行を務めていました。
茶は古田織部に学び、春屋宗園を参禅の師としていましたが、徳川家仕えるようになってからは江戸初期茶の湯界の第一人者として君臨していくことになります。
また遠州は和歌や公家の文化に精通していたため、わびの文化が和歌の精神と通じ合っておおり、王朝風の雅な美意識に、数寄屋建築などの作業奉行としての美意識が加わったものが遠州の綺麗さびと言えます。
展示会のポイント
国宝 志野茶碗
茶の湯の出発は、戦国時代の天下人のもとで利休に代表される商人出身の茶人が茶頭となり
政治的な要素交わりながら発展してきた文化でもあります。
その中で茶碗は地位の権威や名声といった観点からも非常に注目度が高く
それぞれが独特の特徴を持って世に出回っていきいます。
その中でも今回は、桃山時代を代表する国宝の「志野茶碗(銘卯花墻)」の展示がされています。
なんと日本で焼かれた茶碗で国宝に指定されているのは、白楽茶碗(銘不二山)とこの志野茶碗(銘卯花墻)の二つだけなんです。
銘とは、茶碗につけられたニックネームのようなものです。茶碗の形や所有者にちなんで命名されます。
美濃で焼かれたもので、歪んだ器形と表面の鉄絵などは破格の美を象徴とする織部好みであると言えます。
利休の世界観
あなたは千利休と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。
私は一言で表すと「シンプルの中に美しさを見出す天才」だと思っています。
展示室4では、そんな利休の世界観を道具を通して垣間見ることができます。

上の写真は「紹鴎黒大棗」で無駄がなく洗礼された作品となっています。
最近よく耳にする「ミニマル」「ミニマリスト」といった考え方の前身とも感じ取れるかと思います。
また利休は「黒は古き心なり(黒には古きものを求める心がある)」という言葉を残していますが、質感と漆黒という、集中力が研ぎ澄まされる仕様になっていると感じました。
私の人生のテーマに「シンプルに生きる」というものがありますが、これも利休先生の世界観から影響を受けた1つになります。
まとめ
さていかがだったでしょうか。
今回の茶の湯の美学ー利休・織部・遠州の茶道具ー展は、なかなか見られない国宝茶碗から
茶人のそれぞれ特徴のある道具をじっくりと堪能できるまたとない機会となります。
茶道に少しでも興味のある方や、実際にお稽古されている方まで新たな茶道の歴史を知るきっかけになるかと思います。
ぜひ素敵な世界観に触れて、先人の考えに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
それではまた次回、達者でな!!!